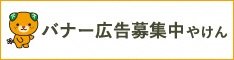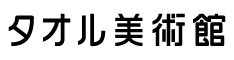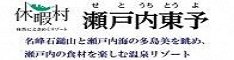【愛媛県伊予市】大洲街道沿いの郡中・灘町~江戸・明治・大正・昭和のまち歩き~
2025.02.07
はじめに

伊予市の中心街、郡中・灘町。江戸時代より、官ではなく民間主導
栄養学の創始者・佐伯矩博士と栄養寺
栄養寺は、伊予市灘町を拓いた宮内家の菩提寺(先祖代々のお墓が
当時の郷土を育てた学者たちの墓

本堂の左手には、六角柱笠つきの宮内清兵衛夫妻の墓、その左に兄
珍しい寺名
幼少時代から北山崎村で育った栄養学の創始者・佐伯矩(ただす)
また佐伯矩博士は、大根の消化酵素ジアスターゼを発見し「栄養学
また佐伯矩博士は、大根の消化酵素ジアスターゼを発見し「栄養学
火防地蔵尊(ひぶせじぞう)

参道入り口にある火防地蔵尊(ひぶせじぞう)は、享保6年(17
灘町は独特なスタイルの町家

さて、JR伊予市駅から西へ延びる”国鉄通り”とそこから北へ延
灘町に並ぶ家々は通りに面した間口が狭く、奥行きがかなりある細
これは町割りを行ったのが、代官などの権力者ではなく地元豪商だ
灘町に並ぶ家々は通りに面した間口が狭く、奥行きがかなりある細
これは町割りを行ったのが、代官などの権力者ではなく地元豪商だ
手づくり交流市場「町家」
数奇屋風の佇まいを持つ”町家”がモデル。販売コーナーには地元
岡部仁左衛門・銅像
黒住教郡中教会所の境内に立つ、削り節の創始者・岡部仁左衛門の
山惣商店

文久元年(1861)に建てられた旧旅籠で、現在は醤油と肥料の
つたや旅館
灘町商店街の中央にたたずむ旅館。昔ながらの純和風旅館と現代の
平久
創業は江戸時代末期といいますから、150年以上も前から灘町の
郡中まち元気サロン 来良夢
1911(明治44)年に伊予農業銀行郡中支店として建てられた
常世橋(とこよばし)
灘町の入口にある明治時代の橋柱跡です。昔、このあたりに梢川と
郷土銘菓こんだ
こちらも老舗の和菓子屋さん。創業は約70年前なんだそうです。
篠崎ベーカリー
創業は明治25年と言いますから、今から130年以上も昔からあ
からき天ぷら
こちらも老舗、創業60年の人気天ぷら屋さんです。人気メニュー
おわりに
2024年11月に行われた、愛媛県主催の”えひめ景観シンポジ
愛媛県の中央に位置し、東予からでも南予からでも、高速道路イン
愛媛県の中央に位置し、東予からでも南予からでも、高速道路イン

記事投稿者:かず
ひめ旅部のかずです。生まれも育ちも愛媛県は伊予市。「伊予の本気」をお届けできるよう県内各地に出没中です。ひめ旅部の記事をきっかけに、カメラを持ってお出かけしていただけると嬉しいです!きっと、あなたの知らない愛媛が待っている?!