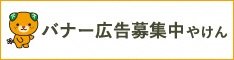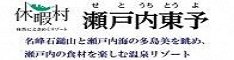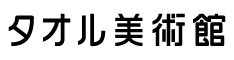【愛媛県伊予市】双海のシンボル本尊山(ほぞんさん)
2025.03.31
山頂には中世の城跡が残る本尊山(ほぞんさん)

伊予市双海町上灘の北西部にあり、昔からこの地域のシンボルでも
先日、テレビのロケでご一緒した、南海放送のえがわさゆりさん“
登山の出発地点は麓にある天一稲荷神社。

途中、ファンタジーのような狭い道もあります。

ところどころ急斜面もあって、ロープが張られています。

山頂付近には、天空の鳥居が立っていて、中世に建てられた由並本

山頂からはほぼ360度のパノラマで、眼下に広がる伊予灘のロケ
河川工事や道路工事に使われた石切り場
さて本尊山の麓には、石切り場の跡が残っています。明治時代から
本尊山麓の石材を使った由並小学校の石垣
かつては700人を超える児童で手狭となったことから、昭和2年
由並小学校のクスノキ
昭和5年(1930)創立時からの校樹だそうで、高さは11m。
日露戦捷(せんしょう)記念碑

こちらも由並小学校の石垣にある記念碑です。書は四国の師団長だ
美しい景色を見せる灘町の鉄橋
また麓には、長さ134m、上灘川を跨ぐJR予讃線鉄橋がありま
おわりに

上灘川の右岸に聳える本尊山。廃城後400年以上が経過していま




記事投稿者:かず
ひめ旅部のかずです。生まれも育ちも愛媛県は伊予市。「伊予の本気」をお届けできるよう県内各地に出没中です。ひめ旅部の記事をきっかけに、カメラを持ってお出かけしていただけると嬉しいです!きっと、あなたの知らない愛媛が待っている?!